対馬丸記念館に行ってきました ボランティア 加藤有子

小桜の塔

小桜の塔 弔歌

合唱。 取材の人たちがどっと前に出てきたので、すきまから写真を撮りました。
昨年に続いて今年も沖縄那覇市の対馬丸記念館に行ってきました。今年は母も一緒です。
疎開する子供たちを乗せた対馬丸が攻撃されて沈んだのは1944年(昭和19年)8月22日。今年(2014年)で70年になります。
8月22日、小桜の塔で行われた慰霊祭に、母とともに参列させてもらうことができました。
沖縄の戦没学童の慰霊塔、小桜の塔は、対馬丸記念館を取り囲む旭ヶ丘公園の中にあります。
慰霊祭の中で、子どもたちの合唱があります。小桜の塔にきざまれている「弔歌」も歌います。これの作者山崎敏夫、というのがじつは私の母方の祖父です。
つしま丸児童合唱団は、対馬丸の沈没で犠牲になった子どもたちの通っていた小学校の生徒を中心として構成されています。あんな年頃の子どもたちが亡くなったんだねえ、と、隣に座っていた母が言いました。対馬丸記念館で見た遺影を思い出して、そうだね、と答えました。
「放蝶」にも参加させてもらいました。オオゴマダラ、という、白くて大きい蝶を放すのです。「オオゴマダラ」ときいて、母は、「…ごまだれ?」って言ってた。違います母上。
式の進む間、オオゴマダラたちは虫かご(といってもふた以外は透明なプラスチックのやつ)の中でばたばたとしていました。
係の人が、虫かごに手を入れて、はねの真ん中あたりを2本の指で挟むように捕まえて、胴体をこちらに向けて差し出してくれます。それを恐る恐る受け取って、胸のあたりと、はねの付け根をつまむようにして持ちます。オオゴマダラのはねは、厚みがあって結構しっかりしていて、粉っぽさはありませんでした。まわりからは、「蝶の顔なんかはじめて正面から見たわ」とか、「元気がいいわ」とか、「飛ぼうとしている」とか聞こえてきますが、私のところに来た蝶はとてもおとなしく、はねも脚も動きません。それでも、カウントダウンの後「放蝶」の掛け声に合わせて手をはなしたら、上に向かって飛んで行ってくれました。よかった。
翌日の「琉球新報」には放蝶をしている合唱団の子どもたちの写真が載っていましたが、あの、後ろのほうで、私の手からも蝶が飛び立っていたのでした。
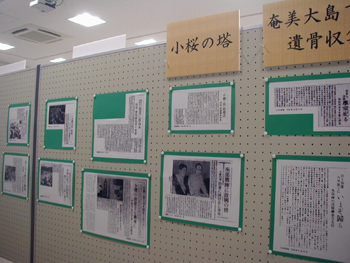
展示のようす

琉球新報 1954年5月2日夕刊
慰霊祭の前に、対馬丸記念館の展示を見てきました。
22日からの新しい展示(資料収集が語る「対馬丸」と「小桜の塔」Part1)では、小桜の塔ができたいきさつを書いた新聞記事が紹介されていました。
愛知県の丹陽(たんよう)村(今は、一宮市丹陽町)に「すずしろ会」を作った河合桂氏の尽力で、沖縄に戦没学童の慰霊碑(小桜の塔)が作られた、という内容です。「すずしろ会」だけで援助するのではなく、桑原愛知県知事とか、草葉厚生大臣にも話を持って行って、PTA、教職員会、校長会からも賛同を得て三十万円集め、それによって小桜の塔の建立の動機が作られた、と書いてあります。
文章の最後のほうに、「(愛知)県立女子短期大学山崎敏夫教授」(←祖父です)の名と、その「弔歌」も出ています。
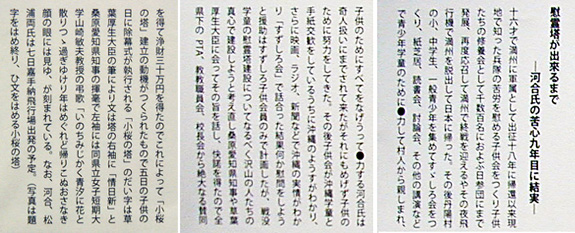
パネル(部分) 琉球新報1954年5月2日夕刊の記事の後半を書き写したもの




22日午後からは首里城で観光、のはずが。タクシー降りて、いちばん手前の守礼門までもたどり着いていないのに、母が、ここで待ってるから一人で見てきたら、って、茶店に入ってしまう。(戻ってみたら、ぜんざい食べてました。沖縄風の、氷の乗ったやつ。)
去年一人で来たときは入場料を払って中まで見たのですが、今回は、無料で入れる所まで行ってきました。
守礼門では、写真も撮りました。去年はカメラを持たずに沖縄に来たので、写真を撮れなかったのです。
ほかにも「門」はあるのですが、灰色の石垣の途中に人が通れる穴をあけたタイプのものが多いのです。そういう門をいくつか見た後で守礼門を見ると、道の途中にあって、細い4本の脚で支えられているような形が、とても新鮮に思えたのです。(去年、初めて見た時の感想です。)
白地に赤と緑のラインの幾何学模様も、軽やかな感じで、いいと思いました。