◆2014年・夏の戦争体験者による語り◆8月1日~15日

8月1日から15日、夏の恒例企画「ピースあいち語り手による戦争体験のお話」が行われました。毎回たくさんの方にご参加いただきました。語り手のお話を、ピースあいちのボランティアが報告します。
8月1日(金) 今村 實さん(81) 「学童疎開・空襲」

私は小学6年の時に母の在所に疎開しました。日本のデンマークと言われた安城市です。友だちと会えなくなり、淋しい思いをしました。私が遭った東南海地震は、終戦の前の年、昭和19年12月8日のお昼過ぎのことでした。
昼ご飯のあと、農作業をしていました。小さな子がひっくり返っていました。学校から低いところの集落では土煙が出ていて、半壊、全壊の家が見られました。
1か月後の1月13日の夜半、午前3時半ごろ、三河地震が起きました。130戸の集落ですが92戸が全壊、130人が亡くなりました。死者は、矢作川の河川敷で火葬にしました。無残な光景であり、寒々としていて怖い思いでした。名古屋から集団疎開した先のお寺も倒れ、55人の生徒が亡くなりました。
4月に浄心中学に入学しましたが、すぐに勤労動員で紡績会社に。5月14日の空襲では、お城が焼けていてびっくりしました。我が家も見当たらず防空壕もわかりません。そこで父と出会いました。そのあとは、親戚の家を転々として、終戦の日を迎えました。
8月5日(火) 塩澤君夫さん(90) 「学徒出陣」

昭和18年9月に一高を卒業し東北大学に入学するが、1年しか大学に行けず、昭和19年10月に前橋予備士官学校に入る。米軍戦車が上陸したら、穴に潜んでいて戦車を爆破するという本土決戦を想定した厳しい訓練を受けた。その後、千葉へ将校として配属される。
その中隊で「特攻志願」と書かなかったのは自分一人だけ。上官が刀を抜き、「非国民だ。命が惜しいのか。首を出せ」と迫ってきた。志願した人たちも本音ではそう思っていないのに、そうせざるを得ない雰囲気があったのだ。
こんな戦争はだめだという気持ちを持っている人はたくさんいたが、表には出てこなかった。国のために死にたいなんて思っていないのに本音を出せないというのが実態だった。
8月6日(水) 木下冨枝さん(78) 「広島原爆」

8月6日午前8時15分、警戒警報解除の時に読書をしていたら、突然真っ暗になり、強烈な光線と揺れ、地響きに驚き一瞬「天皇陛下万歳!」と叫んだ。(当時国民、特に女性は死ぬときには、そう言うように教えられていたからです)。
家は爆心地から1.2㎞の所で、家屋の下敷きになった身内の人たちを掘り起こす様を見ていた。親戚の家に引っ越す途中で見た、川の中に死にかかって助けを求めて叫んでいる無数の人々、お化けのような姿態の人々の様子は今でも頭に残っている。
姉は被爆でできたケロイドを隠すためにいつも和服だった。その姉も悪性腫瘍により9年前に亡くなった。自分もいつ原爆症になるか心配はつきない。心からノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキと訴えていきたい。
8月7日(木) 田中逸郎さん(84) 「学徒動員(豊川海軍工廠)」

8月7日は豊川海軍工廠が空襲を受けた日。工廠では機関銃の弾丸の作成に携わっていた。8時間3交替制でほとんど立ちっぱなし。加えて食事は量も少なく貧弱で、イナゴの空揚げやかぼちゃの種までおかずにした。寮ではノミ・シラミで眠れない日々が続いた。戦争とは本当につらく悲しいものである。
7日は朝8時頃から空襲が始まり、私は少しでも遠くへ逃げた。爆撃後工場に戻ると、体がバラバラになって死んでいる人も見た。悲惨この上ない。
戦争とは残酷で悲しいものである。国民の人権もないがしろし、多大な惨禍をもたらす戦争は二度と起こしてはならない。
8月9日(土) 中村桂子さん(61) 「父の沖縄戦を語り継ぐ」

父、日比野勝廣は、1944年8月19日、中国戦線から対馬丸で沖縄へ。沖縄へ着いたときは「竜宮のようだ!」。それが1年後には…。
1945年4月、嘉数高地、戦車での体当たり攻撃の命令を受ける。5月には米軍の攻撃を受け右腕に負傷。一緒にいた人が肉切れになり散り散りになりソテツの木にかかっていた。まわりは死体だらけ、頭がとび、手足がバラバラ。南風原陸軍病院への移動中、お腹から赤ちゃんが飛び出て、亡くなっている母子をみた。糸数アブチラガマでは、破傷風がひどくなる。看護婦さんにピンセットで「ウジ」をとってもらう。自決用の青酸カリを渡されるが、震えがあり飲むことができない。自分の指が見えないくらい真っ暗。爆弾の爆風で転がり落ちたところに水があり生き延びた。負傷兵1000名余。生還は9名。
戦後も父の苦しみは続いた。何の恨みもない人をなぜ殺したのだろう。自分だけ生きて悪かった。「今日はなあー」と毎日が誰かの命日だった。「戦争は勝っても負けても悲惨だ」「命が大事!平和を愛し戦争を起こさない努力を!」父の想いをバトンタッチして語り継いでゆく。
8月10日(日)筧 久江さん(82) 「学徒動員・空襲・疎開」

(ご自分の成育史の観点から戦争体験を語られた)。
1931(昭和6)年生まれ。幼稚園時代に南京陥落、提灯行列に参加した。小学校4年の時に国民学校と改称され、「少国民」と呼ばれた。6年生では大東亜共栄圏について教えられ、以後、国語・音楽・歴史・修身の4科目で徹底的に軍国主義教育を受けた。1944年市立第三高女に入学、間もなく勤労動員で三菱電機(東大曽根)へ。翌年1月23日の空襲では、防空壕で48人が亡くなった。
8月12日(火)中川礼治さん(84) 「学徒動員・空襲」

終戦時は15歳、愛知一中に通っていた。あの「生徒総決起集会」に参加していた。家に帰り、母に予科練に行きたいと言ったところ、「犬死するな」と言われ、激怒して母に向かって「非国民か!」と言ったことを覚えている。年齢が2か月足りなく、「予科練」行きから外され、本当に悔しいと思っていた軍国少年だった。
中学2年から高蔵寺の弾薬庫で高射砲の弾をつくった。牛車に積んで一人で駅まで運ぶ途中、艦載機の機銃掃射に遭い、牛車の下に潜って助かった。軍隊だから昼は米の飯だが、夜朝は土手の酸い葉をかじった。サツマイモ一つで過ごせと言われた日々だった。
8月13日(水)北村守男さん(79) 「縁故疎開・暮らし」

小さい頃、道で「犬とり」を目撃。犬の口の中に針金が入れられ、血が流れていた。話を聞くと兵隊さんの防寒具に犬の毛皮が使用されるとのことだった。
小学校3年になり、三河川原町へたった一人で縁故疎開。最初は「都会っ子!」と呼ばれ、いじめにもあったが少しずつ仲良しに。夢は兵隊になることだった。
豊橋や岡崎が空襲にあい、真っ赤に燃えるのを見た。東南海地震や三河地震も経験。畑に防空壕を掘るのを手伝ったり、疎開先の家族の子どもの面倒をみたりした。
終戦後帰った南区には何もなかった。母に聞くと、「白鳥橋は死体の山だった」と。学校は校舎も教室も机も教科書も文具もなし。先生の話を聞くだけだった。
8月14日(木)並木満夫さん(91) 「東京大空襲」
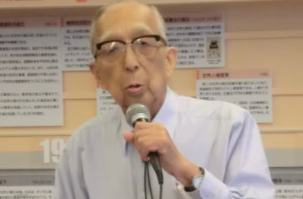
サイパン島の陥落により大型爆撃機B29の飛行が日本まで可能となり、本土空襲が1945年から本格化した。
3月10日の東京大空襲。アメリカ軍は下町にある町工場(中小企業)が軍需産業の生産拠点となっているためと発表しているが、下町は一般民家(木造住宅)が多数密集しており、使用された焼夷弾攻撃は、明らかに木造家屋を焼き払うこと、民間人の殺傷を目的としていた。
同級生の安否を確認するため街に出ると、あちこちに死体がころがっていた。隅田川に差し掛かると橋桁に大勢の人が折り重なって死んでいた。戦争とは直接関係のないお年寄り、女性、子ども、病人などが犠牲になる悲惨。むごたらしいものである。特に空襲は無差別攻撃であり、人道上も問題の多い作戦である。
8月15日(金)小島鋼平さん(82) 「学童疎開・空襲」
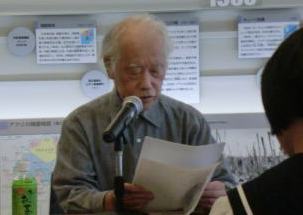
戦争がはじまり、南京が陥落したときに饅頭が配られました。戦争に勝つと饅頭が食べられました。「教育勅語」が奉読されるときには、頭を下げなければなりません。その頭が高いと、「不忠だ」としかられました。
昭和15年は、建国2600年の年で、「紀元二千六百年」という歌が作られ、大人たちは日の丸の小旗を振って市中を行進していました。翌年には「小学校」が国民学校」と改称、私たちは「少国民」と呼ばれ、天皇のために働くよう、勉強よりも身体を強めるようにと教えられました。
昭和19年3月になると、小学3年から6年までの学童は疎開。名古屋市では121校、34000人が、愛知・岐阜・三重の田舎に疎開したのです。私たちは、幡豆郡吉良町のお寺や神社、旅館に。その年の12月7日の「東南海地震」と20年1月13日の「三河地震」、二つの大地震に見舞われました。死者も多く民家も数多く潰れました。学童の死体は棺桶で帰名しました。私たちは、物陰で泣いていました。
B29による名古屋への空襲が始まると、名古屋を心配しながらも飛んでいくB29の美しさを眺めていました。