鏡のなかのニッポン
理事 ピースあいち調査研究会 西形 久司
皆さんも、お出かけ前に、一度は鏡の前で身だしなみを確かめるでしょう。人前に出て恥ずかしくないかどうか、鏡に映った自分の姿を他人の眼でチェックしてみるのですね。人に笑われたり、あるいは人に不快な思いをさせたりしないための、いわば社会人としての最低限のエチケットですね。いままでそのまま外に飛び出していった子どもも、鏡の前に立って一度自分を鏡に映してから出かけるようになったりすると、親だったらわが子もおとなになったなという感慨にふけることでしょう。 他人の眼に自分がどのように映っているのかのチェック、難しい言い方をすると、「他者の眼による自己像の点検」ということになるでしょうか。この他者の眼で自分を見直すということは、とても大切なことだと思います。ときどきこのようにして自分を見直すということをしておかないと、うぬぼれや慢心に陥っている自分に気がつかないままになってしまうかもしれません。
他者の眼で見直すことが大切なのは、個々人に限ることではないと思います。社会や国というレベルでも、一歩外から自分たちを見直してみることは必要なことです。
私自身がこのような思いを強めたのは、実は3・11がきっかけです。原発事故で天文学的な数値の放射能を地球環境に向けて撒き散らしているにもかかわらず、フレンドリーさを前面に押し出した「トモダチ作戦」なる怪しげなものが登場し、日本中のマスコミがこぞって「がんばろう、ニッポン」キャンペーンに熱狂しているさなか、日本の私たちは、世界中の人々が心から日本のことを心配してくれているかのような気分にさせられていました。日本の戦時体制の歴史を多少かじっている私は、「これって戦時体制なのじゃないか?」という疑問が自分のなかでふくらんでくるのを感じていました。
インターネットでニューヨーク・タイムズのサイトを覗いてみると、日本政府のスポークスマンの発表などはなから当てにしておらず、大統領の周辺は独自に収集した情報に基づき、軍や原子力関係の機関に対してかなり緊迫した指示を出しているようでした。日本のマスコミが伝えるフレンドリーなアメリカなど、そこには微塵も存在していませんでした。私たち日本人は、ものの見事に「情報鎖国」のまっただなかに封じ込められていたのでした。他者の眼などどこかに吹っ飛び、唯一絶対の自己像に没入しているさまは狂信的ですらありました。
歴史家のはしくれとして、このとき日本と世界で進行していたことを、同時代史の光景として記憶にとどめておこうと思い、私の乏しい「おこづかい」の範囲で文献をあさりました。私がとくに関心をもったのは、外国人の日本を見る眼でした。
FCCJ(日本外国特派員協会)の独自集計によれば、3月12日~4月1日の間に、主要12か国だけでも40万人以上の外国人の日本在住者が出国していました(『ジャパンタイムズ・ニュースダイジェスト』2011年8月臨時増刊号)。次の瞬間にどのような不測の事態が起きないとも限らない危ない国ニッポンから、がんばって出国していたのでした。
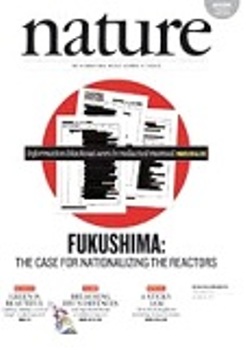
英国の権威ある科学雑誌『ネイチャー』2011年12月15日号の表紙は、日の丸の真ん中に東京電力が当初公表した「塗りつぶされたマニュアル」が配されているという構図になっていました。さらにその号の「臨界物質」と題した論説記事では、事故から9か月を経てもどのような事態が進行しているのか、いまだに日本政府が国外に向けてまともに説明できないのは、政府や業界から独立した科学者の助言を受け入れないからであり、誤った情報に基づいた日本政府のスポークスマンの発表は、彼らを「馬鹿で無責任でウソつき」に見せてしまうと痛烈な批判を展開していました。
日本の国内外の報道のズレという点では、次のような外国人研究者の興味深い研究も出されています。事故直後(2011年3月17・24・31日の3日分をピックアップ)の日米間の原発事故関連のウェブサイト上での報道を対比してみると、日本の「朝日」「毎日」「読売」の主要3紙では原子炉のダメージへの関心が強いが、アメリカのメディアでは放射能汚染に強い関心をもっているというのです(Leslie M. Tkach-Kawasaki ‘MARCH 11, 2011 ONLINE―Comparing Japanese newspaper websites and international news websites’; Kingston2012 pp.109-123)。日本の私たちは、自分たちのことを原発事故の「被害者」だとばかり思っていたのですが、外国の人たちは「加害者」だと見ていたのでした。
こうして外からの視線にさらしてみると、いかに私たちの自己像が歪んだものになっているかが明瞭に見てとれます。「情報鎖国」の怖さを実感することができます。
さて。3・11以後のこの国の様子をみてみると、どうも日本の私たちは3・11の経験から虚心坦懐に学んだとは言えないように思います。
このたびの特定秘密保護法案は「情報鎖国」促進法案ともいうべき内容です。私たちはほとんど気づいていないのですが、私たちの国は情報公開という点ではかなりの後進国であると言わざるを得ません。近年の調査でも、政府機関の公文書の廃棄量は膨大で、とりわけ外務省の廃棄量がダントツだそうです。どうも後世の歴史家にチェックされるのを恐れているとしか思えません。都合の悪いことはなかったことにしようという、およそ公的な立場の人たちにあるまじき姑息な態度に終始しているのでなければよいのですが。
これは近代日本の伝統というべきものなのかもしれません。私は自治体史の編纂に関わっているのですが、たとえば国立公文書館で戦時下の歴史を調べようとすると、かなりの部分を「返還文書」に頼らざるをえません。
「返還文書」とは何か。敗戦直後、膨大な公文書が焼却処分されました。とにかく手当たりしだいに燃やしてしまったのです。遅まきながら占領軍が進駐してきて、国際軍事裁判の証拠とするために、政府や軍が焼却しきれなかった残余の書類を接収しました(1945年11月)。その後、1956年に旧軍関係のものが防衛庁に返還され、国立公文書館には1974年に返還されました。要するに、アメリカから接収文書の返還がなかったなら、戦時下の支配体制の歴史に大きな欠落部分ができてしまったかもしれないということなのです。
公文書はとりもなおさず国民の財産ですから、自分たちにとって都合が悪いものでもそれを確実に残し、後世の審判を仰ぐという「公僕public servant」としての責任感・義務感が、どうもこの国には根付くことなく、こんにちに至ってしまったようです。最近とみに増殖してきた、「どこに出しても恥ずかしい」と言いたくなるような政治家や首長が育つ政治風土は、どうもこのあたりに根ざしているように思われてなりません。 その結果、どのような巨大な不幸が自国民や諸外国の人々の身に降りかかるか、それは近代日本の歴史を少しひもとけばたちどころに分かることです。他者からどれほど醜怪に見えようが、まわりの迷惑などいっさいおかまいなしに振舞いながら、私たちは再び「狂信」への道へと突き進むのでしょうか。もういい加減に私たちも、国際社会のなかで他者の眼を意識する年頃になってもよいと思うのですが。
*原発事故報道に関しては、かつて「福島原発事故と『炉心溶融』報道」という論文にまとめてみました(『東海近代史研究』33号2012年)。いちどお読みいただければ幸いです。